急なお通夜や葬式での準備でバタバタした経験がありませんでしょうか。
急に来るのがお葬式です。
そこでこれだけ見ればバッチシなまとめ記事を書きました。
※参列者目線。仏教としてのまとめです。シンプルに結論を書いてます。
こんな人にオススメ
- いつも急にバタバタ用意する人。
- 色々な宗派があるのでどれにすればいいのか迷ってる方。
- 香典の費用は?服装は?焼香は何回?などのマナーがわからない方。
- 式場で親族に何を話せばいいのかわからない方。
- 通夜と葬式の違いがわからない方。
たまにしかない葬式の為、ついつい忘れてしまいます。
なのでこの記事だけを見ればわかるようにしていますので、ぜひ参考にしてください。
通夜?お葬式?告別式?違いと注意点。

通夜とは=一般的には亡くなった翌日に行われる。
葬式とは=通夜の翌日に行われるとむらい
告別式とは=葬式とほぼ一緒。有名人や会社役員等、社会的地位のあった方のお別れ会としてのイメージが大きい。
通夜の翌日に行われるのが葬式と告別式。葬式と告別式に大きな違いはない。
服装の違いはあるのか?
通夜は亡くなった翌日に行われるので、参列者に話が行ってすぐの事。
よって通夜の服装はそこまで気にしなくてよい。と言われる事があります。ただしこれは昔の話。現在では様々な通信手段がある事から、参列者にも通夜に参列するまでに十分な時間があるからです。
なので、今は通夜も葬式も喪服(ブラックスーツかワンピース)が一般的です。
通夜、葬式、告別式等気にせず、全て喪服(ダークスーツやワンピース)で参列しましょう。
香典に関しての注意点と中身
以外と気にするのがお金。つまり香典になります。
香典とは=故人への供養の気持ちを表す物で一般的には香典袋の現金を包んで渡します。
香典は通夜?葬式?どちらに持って行く?
香典は基本的には通夜に持参します。
通夜が行けず告別式(葬式)だけの場合はその時渡しましょう。
通夜と告別式に両方に参列する場合は通夜だけでOKです。告別式は記帳のみOKです。
二回渡すと「不幸が重なる」と言われよくありません。
香典は1回だけ渡す。基本は通夜に持参。
香典の相場は?
香典に関しては、宗派や年齢、立場なのでによってかなり様々な考え方があります。
ここでは色々参考文献を読んで簡単にしました。
絶対守りたいのは奇数です。具体的な数字としては。「3千円、5千円、1万円」
の3パターンです。細かい事を言うと書籍にも色々記載はありますが、
あまり親しくない人=3千円、知人や親戚=5千円、親しき人や親族=1万円
ぐらいに分けてOKです。大事なのは気持ちです。ただ奇数にする事は意識しましょう。
偶数はNG。基本は3千円、5千円、1万円等、奇数にする事。気持ちが大事です。
香典袋に関して
香典袋も色々な種類と書き方があります。宗派によっても違いますが、どれでも通じる物だけ覚えておけば問題無いです。
袋の種類
水引きの香典袋を購入します。コンビニでも売っているシンプルなものでOK
白と黒の水引き袋で、御霊前、御仏前、御香料、等の記載がある袋を購入します。
※水引きとは=下記写真の様に蝶々結びの逆みたいな形状です。

「表書き」と言われる、御霊前、御仏前、御香料、等色々な種類があります。これも宗教によって最善な表書きがありますが、基本的に仏教では「御香料」を使用すれば問題ないと言われてます。「御霊前」も一般的で多いのですが、浄土真宗や真宗では使用しないから「御香料」にしておけば安心です
香典袋に関しては白黒の水引きを購入。表書きは「御香料」にしときましょう。
薄墨は何処まで使う?
香典に関しては表書きは「薄墨」で書きます。なぜ薄墨かと言うと「突然の訃報で涙で墨が薄くなった」と言う説が有力です。
少し大袈裟な気もしますが、一般的に薄墨で持ってくる方が多いので自分だけ通常のペンで書いて持ってくると目立つので辞めましょう。
1本で薄墨と通常ペンと使用できる便利な物もあるので購入しておきましょう。
但し薄墨で記載するのは「表書き」のみ。袋の中にお金を入れる袋があればそこには通常のペンで記載しましょう。相手が香典返し等で使用する為きちんと見えるペンで書きます。
香典袋の一番表は「薄墨」。香典袋の中に記載する時は「通常のペン」。
袱紗(ふくさ)は必要

香典は袱紗(ふくさ)に入れます。当日は受付で袱紗(ふくさ)から香典を出して渡します。
袱紗(ふくさ)に関しては持って置いた方がいいです。葬儀だけでなく結婚式でも使用します。若い頃はまだなくてもいいかもしれませんが、段々となくては恥ずかしい常識になってきます。
なので購入するなら冠婚葬祭の両方で使用できる袱紗(ふくさ)がオススメです。
香典袋はそのまま持って行かず、袱紗(ふくさ)に入れて持って行きます。
葬儀で遺族に話す事。
そこまで親しい仲でなければそこまで話さないが一番正解です。言ってはいけないキーワードが多くて会話困るからです。いわゆる忌み言葉と言われる物です。例えば、「終わり」「別れる」「度々」など繰り返す言葉や終わりを連想させる言葉はNGです。
宗教によっても変わるので話さないが一番です。ご遺族に香典を渡す時に何も言わないのも渡しにくかったりもします。その時は一言二言だけ覚えておきましょう。
「この度はご愁傷様でございます。」
「心よりお悔み申し上げます。」
これだけでいいです。できるだけ他の事は話さないようにします。
基本は話さない。話しても「この度はご愁傷様です。」「心よりお悔み申し上げます。」だけ。
焼香は何回する?
これに関しては結論から言います。
2回にしましょう。
宗派によって考えかたは沢山あります。1回~3回が一般的な為基本は2回でOKです。
ただ抹香(まっこう)はどの宗派でもあるので基本的な動作はおさえましょう。
右手の親指・人差し指・中指の3本で抹香(まっこう)をつまみ、額の高さまで上げます。この動作を「おしいただく」といいます。
「おしいただく」を2回する。これだけでOKです。
葬儀での身なりに関して。

- 服=ブラックスーツ(略式喪服)黒のワンピース。
- シャツ=白
- 靴=できるだけ黒の靴。スニーカ等はNG。ビジネスシューズ可。
- アクセサリー=真珠(黒、白)ぐらい。結婚指輪はOKだがダイヤ等光物はNG
基本は黒、白。光物はNG。「重なる」は忌み言葉となるので重なる真珠もNG。
参列できない場合は弔電(ちょうでん)
通夜は突然やってきます。お世話になった方が遠方の場合は駆けつけたくても無理な場合はあります。
その時は弔電(ちょうでん)を送るのが一般的です。昔は電話で依頼していましたが今ではネットで簡単申し込みできます。
参列できない場合は弔電(ちょうでん)で気持ちを伝えよう。
まとめ
葬儀を参列する事になって焦らないようにまとめました。
簡単にまとめると。
- 通夜→葬式(告別式)の順番で行われる
- 服装は、ブラックスーツかワンピース(靴は男女とも黒の靴)スニーカーNG
- 香典は奇数。3千円、5千円、1万円が基準。関係性による。
- 香典袋は水引。表書きは「御香料」。
- 香典袋は袱紗(ふくさ)に入れて持参する。
- 式場で遺族の方と話す言葉は「この度はご愁傷様です。」「心よりお悔み申し上げます。」だけ。
- 焼香は2回すればOK。
- アクセサリーは基本NG。真珠(黒、白)や結婚指輪(派手な物やダイヤはNG)。
- 参列が出来なければ弔電で気持ちを伝える。
宗教のよって様々な考え方があります。ただ参列する度に宗派を調べて勉強するわけにもいかないので一般的に問題ない事を理解して覚えておけばOKです。
ただ一番は何より故人に対する「気持ち」です。色々なマナーを守るより故人に対する想いが一番です。



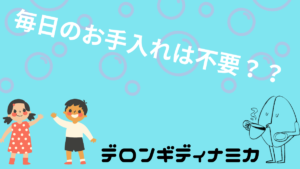

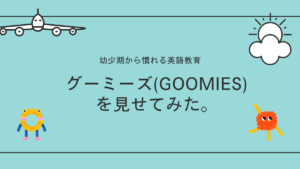

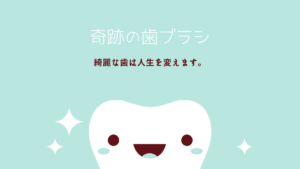
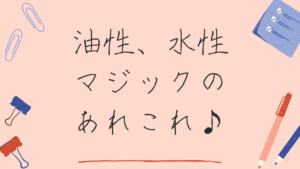
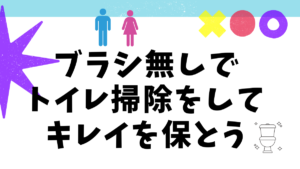
コメント